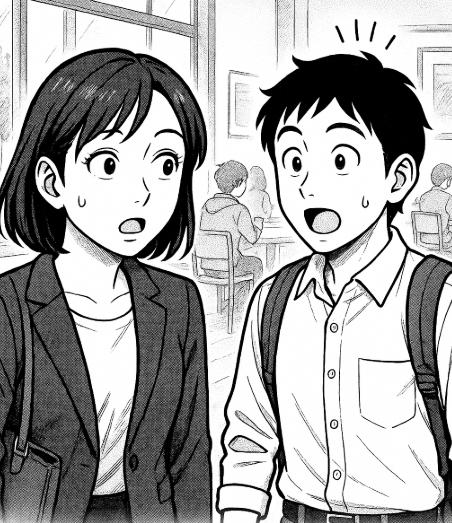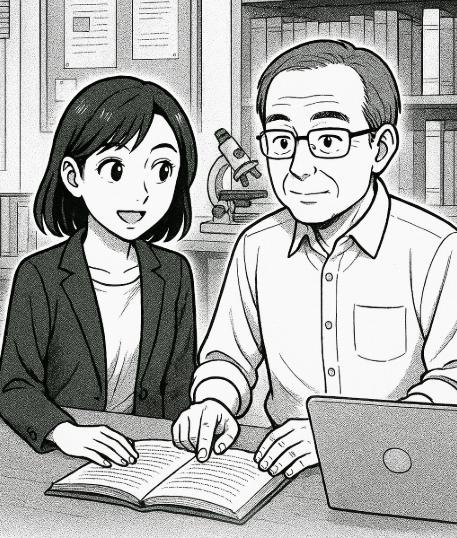久しぶりの地元とジム、そして“再会”
地元に戻ってきて数ヶ月。
都内の仕事に疲れて、一度リセットしたくて選んだ引っ越しだったけど、思った以上に生活は穏やかで、心地いい。
その日、私は新しく通い始めたジムで、いつものように黙々と汗を流していた。
イヤホンをつけて、マシンの上で一定のリズムで走る。誰とも話さない静かな時間が、最近の私には癒しだった。
──だったはずなのに。
ふと、目の前の鏡に映った人影に、心臓が跳ねた。
背の高いシルエット。落ち着いた雰囲気。
あの横顔、見覚えがある……いや、忘れるはずがない。
「……○○?」
声をかけられて、身体が固まる。
振り返ると、やっぱり彼だった。
大学時代、同じサークルにいた先輩。
少し年上で、みんなからモテてた。でも私にだけは、時々やさしくて、意味ありげな視線を投げてきた人。
曖昧な距離感のまま、何も始まらなかったけど──ずっと心のどこかに引っかかってた存在。
「ひさしぶり、だね」
「まさか、ここで会うとは思わなかったよ」
その声を聞いた瞬間、あの頃の私が、胸の奥で目を覚ました。
視線と声に、身体が勝手に反応する
「地元戻ってきたの?」
「うん、ちょっとね。気分転換、かな」
ジムの休憩スペースで、自然に並んで座る。
話してるだけなのに、汗とは違う熱が身体にこもる。
先輩は昔よりも少し精悍になってて、Tシャツ越しの腕の筋肉に、思わず視線が泳いでしまう。
その指先、前はもっと細くて柔らかかった気がする。でも今は……男の手、って感じ。
──その手で、もし私の腰を引き寄せられたら。
そんな妄想をした瞬間、胸の奥がじんわり熱くなった。
「なんか、顔赤くない?」
「えっ!? そ、そんなことないよ……!」
慌てて水を飲む。
けれど、彼の笑った目が私の胸の奥まで見透かしてるようで、逃げ場がなかった。
ストレッチ中の指先と、重なる記憶
「ストレッチ、ちゃんとしてる?」
「一応……でも固くて」
「じゃ、ちょっと手伝ってあげるよ」
そう言って、私の背後に立つ先輩。
ヨガマットの上で前屈した私の背中に、そっと手を添えた瞬間──息が止まりそうになった。
背中から腰へと滑る指。
触れてるのは筋だけのはずなのに、その手のひらが、じわっと体温を移してくる。
「昔から、ここ、固かったよね」
「……覚えてたんだ」
耳元で囁かれたその声に、心臓が跳ねた。
腰に添えられた指が、ちょっとだけ滑ったような気がした。
本当に気のせいかもしれない。でも、私の身体は……確実に反応していた。
──こんな場所で、何を考えてるの。
でも、止まらない。
触れられていないところまで、疼いていく。
ベッドの中で疼く「触れてないのに」
帰宅して、シャワーを浴びて、髪を乾かしながらも、ずっと先輩のことを考えてた。
背中に残った手のひらの感触。
耳に残った声の響き。
寝転がって目を閉じると、あのストレッチの時の空気がすぐに蘇ってくる。
──もし、あのまま手が滑ってたら。
──もし、彼が背中から抱きしめてきたら。
そんなことばかり考えて、息が浅くなる。
太ももに感じる鼓動。熱くなっていく下腹部。
シーツの上で身体をくねらせながら、私は静かに指先を滑らせた。
「……んっ」
声を出すのは怖い。
でも、指を止められない。
先輩の手じゃない。わかってる。
だけど、妄想の中では確かに、あの人の手が私を触っている。
──先輩、あのとき抱いてくれてたら、どうなってたんだろう。
快感と共に訪れる、罪悪感と興奮。
止めたくても止まらない。
だって、私の身体はもう……あの指先に支配されてしまっていたから。
忘れかけてた欲望が、再会で目を覚ました
あの日から、ジムに行くたびに先輩の姿を探してしまう。
偶然のはずの再会が、もう「必然」に思えるほど、私の中で彼が大きくなっていく。
恋じゃない。
でも、欲望だけはハッキリとある。
再会して、ほんの少し触れられただけ。
でも、私の身体はあの人を忘れてなんていなかった。
あの声、あの指先、あの距離。
全部が、記憶の奥にしまっていた“女の私”を呼び覚ました。
そして、気づいてしまった。
私は今、彼に抱かれたいって思ってる──。