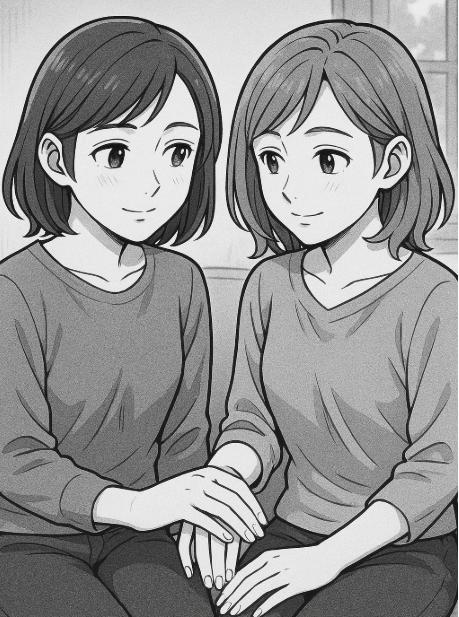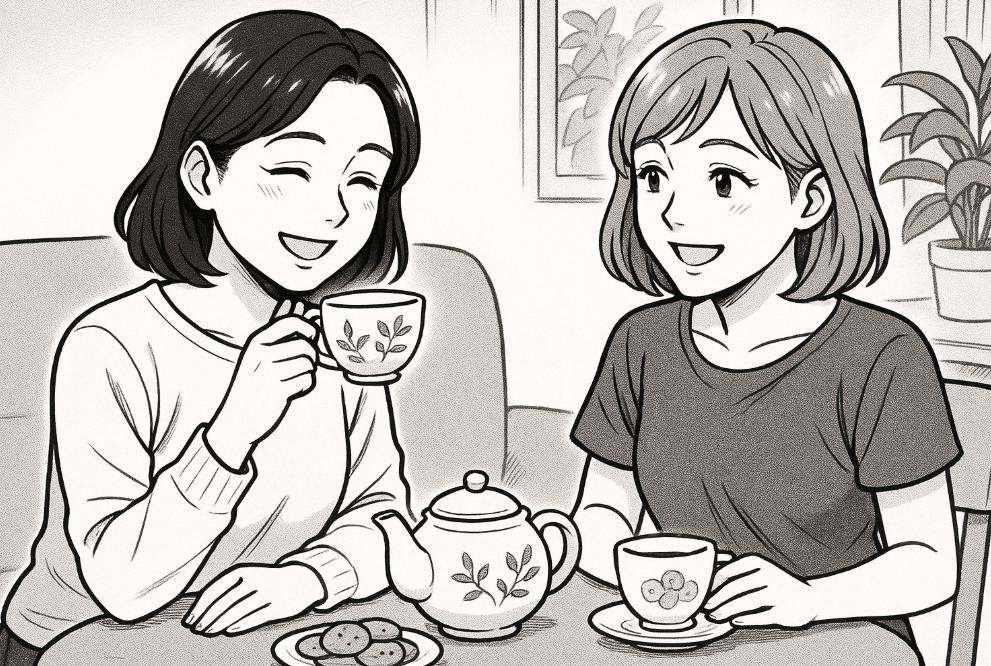
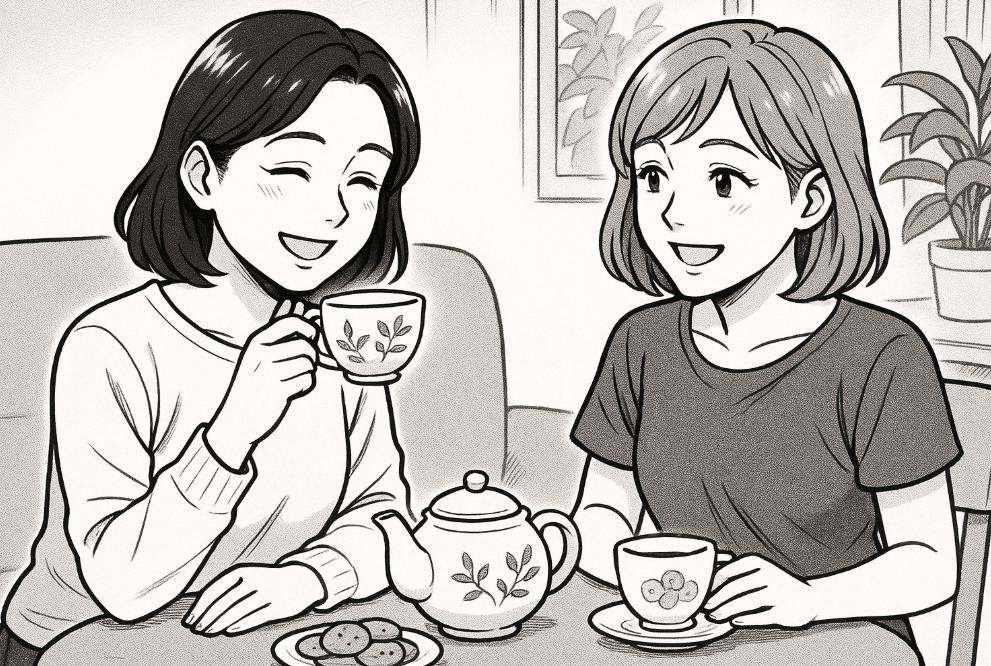
「こんにちは〜。あの……これ、余ったから。よかったらどうぞ」
少し照れたように声をかけてきたのは、隣に住む松岡 梓さん。
私と同じ30代後半で、ふたりの子どものお母さん。
清楚で落ち着いた雰囲気のある人で、近所では“しっかり者の奥さん”として有名だ。
私はと言えば、結婚して12年目、子どもはいない。
夫は仕事人間で、家にいてもスマホかパソコンを触ってばかり。
家庭は壊れていないけれど、どこかすれ違い続けている。
そんな私たちの間に、どこか似た“温度”を感じていた。
「たまには、ゆっくりお茶でもどうですか?」
玄関先でのお裾分けがきっかけで、梓さんと少し立ち話をするようになった。
「お仕事してないんですか?」
「今はしてないんです。結婚してからずっと、専業で」
「そっか……。じゃあ、たまには、うちでお茶でもどうですか?」
意外だった。
でも、なぜか心がすっと温かくなった。
午後のリビング、カーテンを閉めて
その日、私たちは午後の2時すぎから、梓さんの家でお茶を飲んだ。
彼女の家はシンプルで清潔感があって、でもどこか、寂しさが漂っていた。
子どものおもちゃが端に寄せられたリビング。
遮光カーテンが少しだけ閉じられていて、時間の感覚が曖昧になる空間。
「彩香さん、うちの夫……全然、目を見てくれないんです」
ポツリと、梓さんが言った。
「家族としてはちゃんとやってくれてるんです。働いて、子どものことも見てくれて。でも、女としては……なんというか、扱われてないっていうか」
言葉を選びながらも、彼女の瞳の奥には確かな“乾き”が見えた。
「私も……たぶん、似てる」
「うちも……たぶん、似てるかも」
気がつけば、私も同じような言葉を返していた。
「夫に“寂しい”って言っても、うまく伝わらなくて。
言えば言うほど、めんどくさい女だって思われる気がして」
「わかります、それ」
お互いの声が少し震えていた。
まるで、ずっと誰にも言えなかった秘密を、偶然同じ“種類の人”にだけ話せたような、そんな感覚。
「旦那には言えないね、こんなこと」
「もし……夫がこれを聞いたら、なんて言うかな」
「……『そんなことで?』って言うかも」
「うん。絶対言う。
寂しいとか、触れられたいとか、
そういうのを“わがまま”って思ってる」
沈黙のあと、私たちは同時に笑った。
笑いながら、少し泣きそうになっていた。
「この気持ち、旦那には言えないね」
梓さんがそう呟いたとき、私は彼女の横顔を見つめていた。
その瞬間、私たちは確かに、女同士として、何かがつながった気がした。
予感のラスト
「また……お茶しませんか?」
「ぜひ」
そのやり取りだけで、心が少し温かくなる。
でもその奥に、今まで感じたことのない感情の熱が、静かに灯っていた。
友情か、共感か、それとも──
その時はまだ、わからなかった。