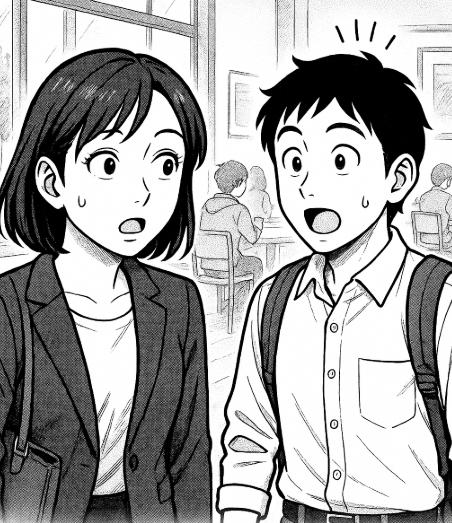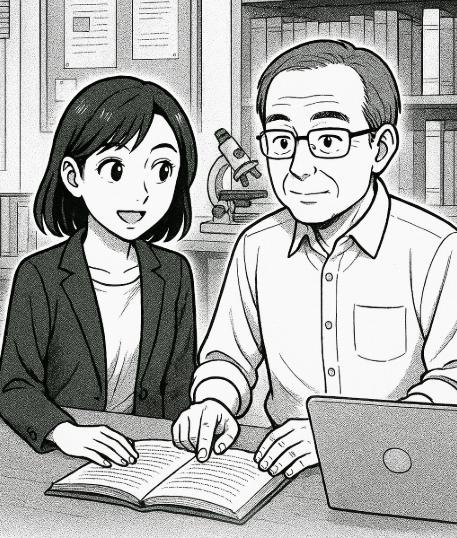1年以上、触れられていなかった
夫とのセックスがなくなって、どれくらい経っただろう。
1年? それとも、もっと?
もう数えるのもやめていた。
最初はお互い疲れてるから、と自然に減っていった。
そのうち、私も「触れられたい」と思う気持ちを、口にするのが怖くなった。
拒まれたらどうしよう。
欲しがる自分が、惨めに見えたくなかった。
だから、自分の“女の部分”は、そっと隠して生きることにした。
母であり、妻であり、社会人であればいい。
でも──
心の奥に、ずっと熱を閉じ込めたまま生きていた。
潤いをなくした下着。
ピクリとも反応しなくなった指先。
「このまま一生、抱かれずに終わるのかな」なんて、本気で思った夜もあった。
そして、ある日。
スマホの広告に出てきた、出会い系アプリのバナーを、“本当に興味本位”でタップした。
本気じゃなかった。けど、寂しかった
若い子向けの軽そうな出会いばかりかと思っていたけど、登録してみると、意外と落ち着いた人もいた。
メッセージが来たのは、27歳の会社員という男性。
私より10歳近く年下。
「落ち着いた雰囲気が好きなんです」
「人妻さんって、なぜか惹かれてしまって」
そんなことをサラッと言う彼に、最初は警戒した。
でも、やり取りを重ねるうちに、少しずつ壁が溶けていった。
「ただ話してみたい」
「誰かと、ごく普通の会話がしたい」
そんな気持ちだった。
なのに、なぜか“会ってみよう”という流れになったとき、私は断らなかった。
本気で求めてるわけじゃない。
ただ、久しぶりにちゃんと女として扱われたかった──それだけだった。
でも、会った瞬間から、全部が狂いはじめた。
見つめられた瞬間、女に戻った
待ち合わせのカフェ。
彼は写真よりもずっと大人っぽくて、会話も落ち着いていて、私の目をずっとまっすぐ見て話す人だった。
「思った通り、綺麗な人ですね」
そう言われて、心がザワついた。
「……そんなことないよ」
そう答える自分の声が、どこか上ずっているのが自分でもわかる。
視線が交差するたびに、肌の奥が反応してしまう。
久しぶりすぎて、男の目で見られることの感覚を、身体が思い出せずに震えていた。
手がふと触れたとき、私は一瞬、息を止めた。
それはただの偶然だったのかもしれない。
でも、その“偶然”をきっかけに、彼は迷わず私の手を握った。
拒めなかった。
むしろ──待っていた。
ホテルへ向かう道のり。
私はもう、ずっと前から身体の奥で火をつけられていた。
あの一瞬で、すべてが溢れた
部屋に入るなり、私たちはほとんど言葉を交わさずに唇を重ねた。
彼の舌がゆっくりと口内をなぞるたび、背中にゾクッとした震えが走る。
服の上から胸に触れられた瞬間、声が漏れそうになった。
たったそれだけのことで、涙が出そうだった。
ずっと、誰にも触れられていなかった。
女として見られることも、感じることも、忘れかけていた。
「……そんなに我慢してたの?」
彼が耳元でそう囁いたとき、堰を切ったように身体が震えた。
彼の手が、腰から脚へ、ゆっくりと滑っていく。
脱がされた下着が、濡れていたのを見て、彼が笑った。
「いっぱい濡れてる。可愛い」
恥ずかしい。でも、嬉しい。
女として欲しがられることが、こんなにも快感だなんて。
彼の舌が敏感な部分を這ったとき、私はたまらず背を反らせた。
感じすぎて、理性なんてどこにも残ってなかった。
もっと触れてほしい。
もっと乱されたい。
1年以上抱かれていなかった身体が、彼の動きひとつで“女”に戻っていくのがわかった。
何度も達した。
何度も彼を求めた。
自分でも驚くほど、貪欲に、濡れて、喘いでいた。
「奥、気持ちいい?」
「……うん、すごい、奥が……んっ、だめ……っ」
私の声がこんなに淫らだったなんて、自分でも知らなかった。
一夜が終わっても、身体はまだ熱い
気がつけば、朝になっていた。
シーツの上、乱れた髪、肌に残る彼の熱。
隣で寝息を立てる彼を見ながら、私はそっと目を閉じた。
後悔は──なかった。
むしろ、ようやく思い出せた。
私は“女”だったということ。
抱かれることでしか、思い出せない何かが確かにある。
心じゃない。言葉でもない。
奥から溢れ出すような快感と、満たされる静寂。
それが、今の私に必要だった。
もう、“ただの人妻”には戻れない。
私は、女でいたい。
まだ終わりたくない。
もう一度、抱かれたい。
そう願ってしまった自分が、正直すぎて怖かった。
でも、その正直さこそが──
1年以上、塞いでいた私の扉を開けてくれた気がした。